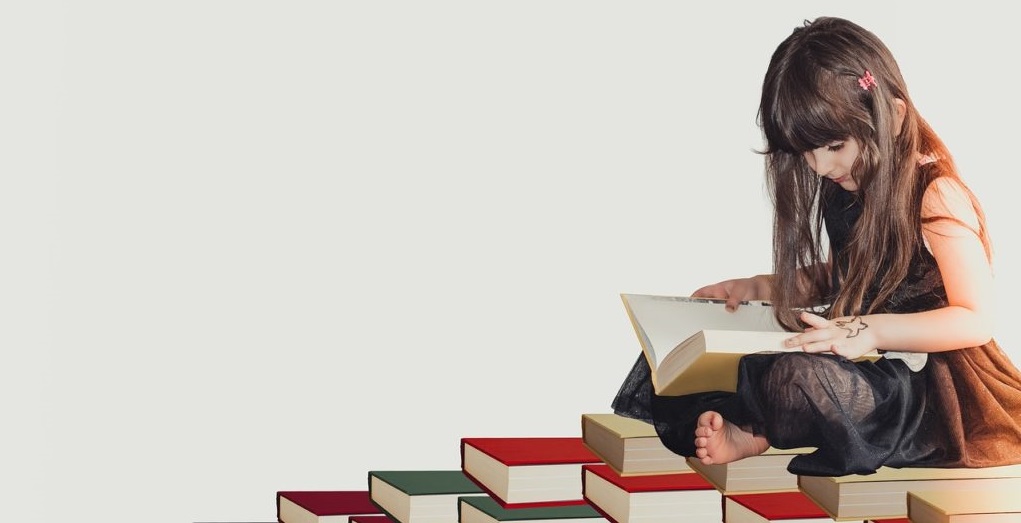「スマホでできる医療経営士問題集」(以下、本サービス)購入に対する注意事項(ご利用規約)
本サービスをご購入いただいた方は、注意事項(ご利用規約)をご確認いただいたものといたします。
ご購入後のトラブルの予防のためにも、ご購入前に必ずお読みいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
注意事項(ご利用規約)
1.本サービスは医療経営士試験の合格を保証するものではありません。試験結果については本サービス及び製作者は一切の責任を負いません。
2.本サービスの情報については細心の注意を払っていますが常に正しいとは限りません。本サービスのご利用によって生じる如何なる損害、トラブルについて、本サービス及び製作者は一切の責任を負いません。
3.本サービスの動作確認状況は商品紹介ページに記載の通りですが100%の動作保証はできかねます。ご購入前に同ページ内のデモで動作に問題がないことを確認し納得の上でご購入下さい。
4.本サービスのご利用はインターネット接続が必要です。ご利用の環境による接続不良や動作速度低下など、インターネット接続に関するトラブルについては本サービス及び製作者は一切の責任を負いません。
5.本サービスの決済はクレジットカード(VISA/JCB/Master/AMEX/Diners)決済サービス(Stripe)を使用しています。クレジットカード情報は当サイトには一切保存されませんのでご安心ください。
6.本サービスの特性上、ご購入後の『キャンセル/返金/返品/交換』はできかねます。ご購入前に商品紹介や本注意事項をよくご確認ください。
7.本サービスは製作者が利用者に通知することなく本サービスの内容を変更し、または本サービスの提供を中止することができるものとし、これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
8.本注意事項(ご利用規約)は予告なく変更することがありますが。その場合は利用者は変更後の注意事項(ご利用規約)に従うことに同意するものとします。変更はご利用者・製作者双方が気持ちよく本サービスを利用できることを目的とする内容に限りますが、ご納得いただけない場合は本サービスのご利用を控えていただくことになりますのでご了承ください。
9.利用者は、製作者の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
10.本規約の解釈にあたっては日本法を準拠法とします。本サービスに関して紛争が生じた場合には、製作者の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
11.製作者の債務不履行責任は、製作者の故意または重過失によらない場合には免責されるものとします。本サービスの著作権は製作者に属しており、製作者の同意なしに本サービスの販売および再配布、及び委託受注など商品を利用したサービス及び商売を行うことは禁止しております。また、商品及びその一部を再配布及びダウンロードできる形で公開することを禁止します。
本サービスが皆様のお役に立てれば幸いです。