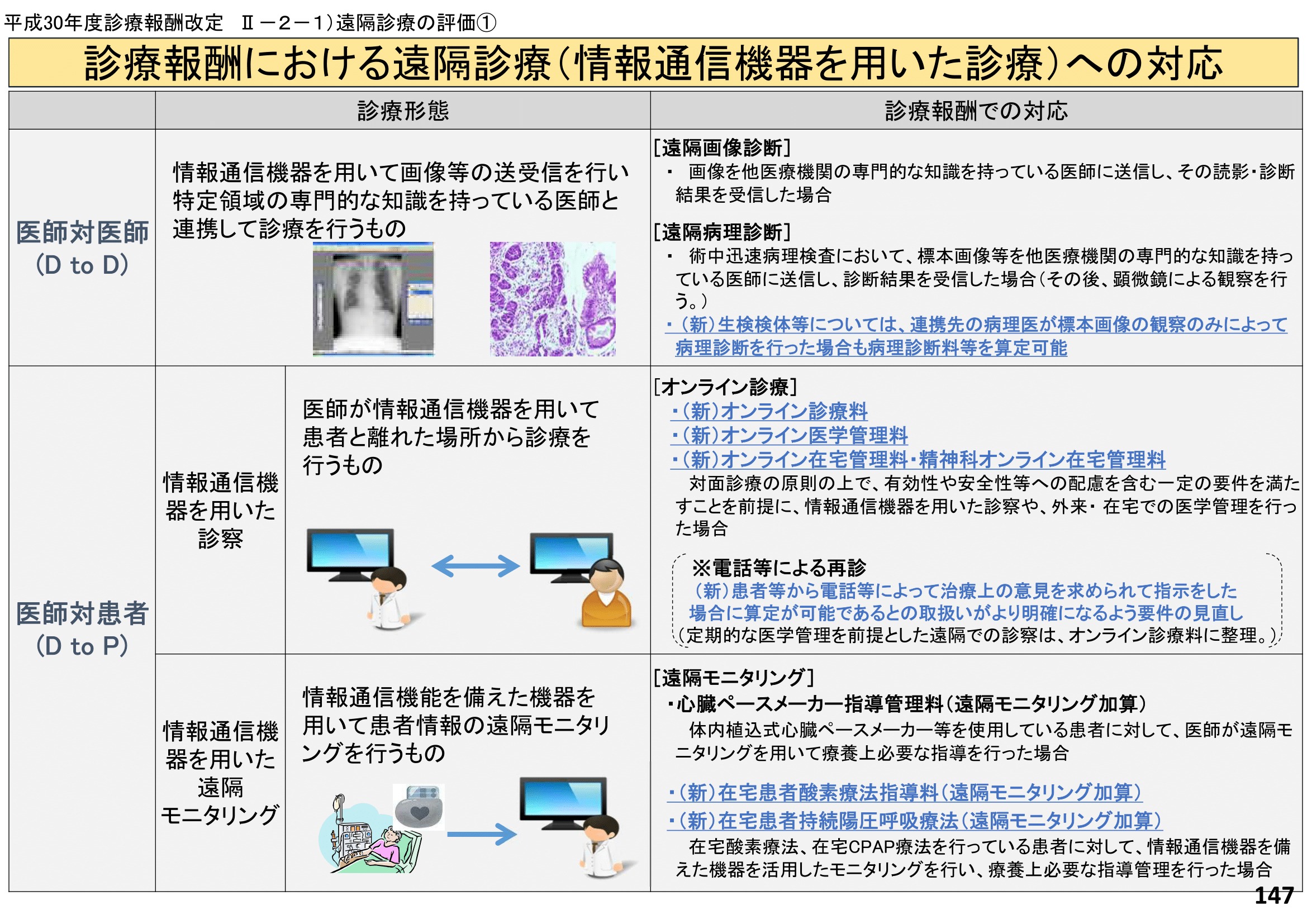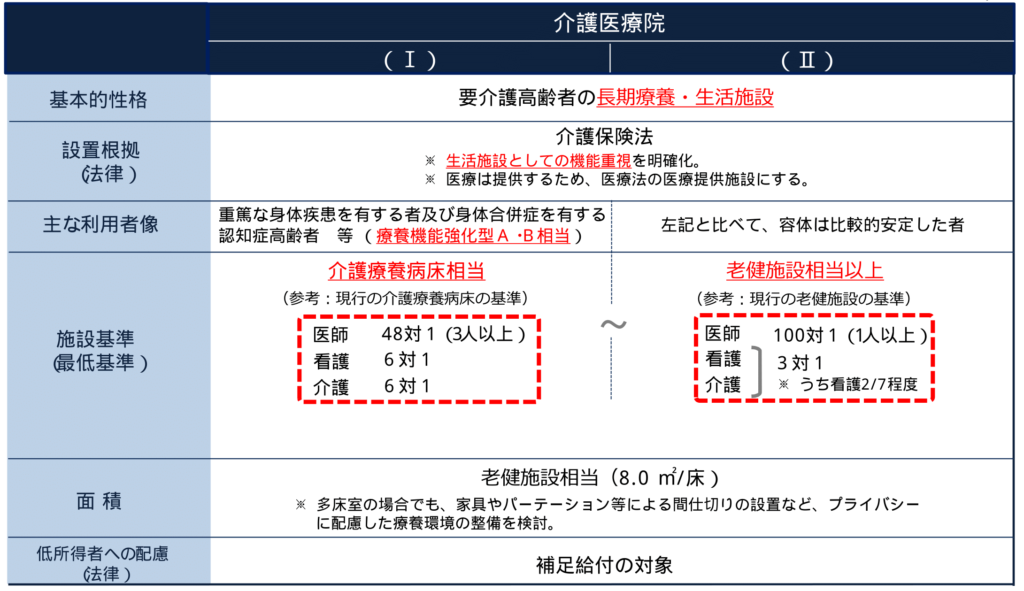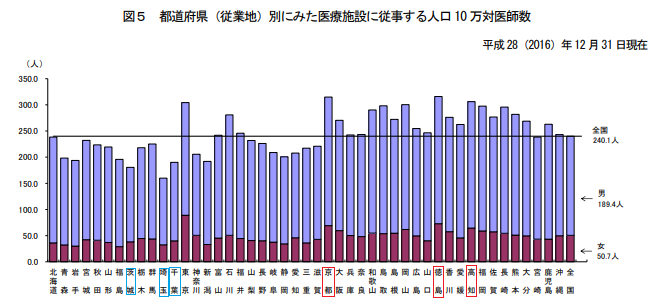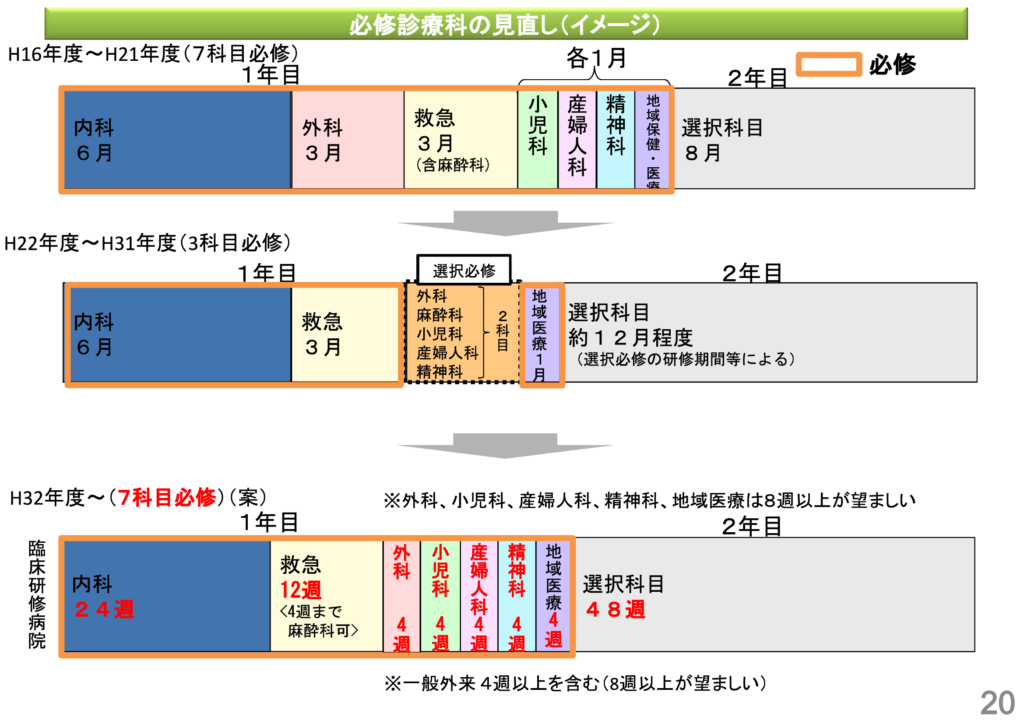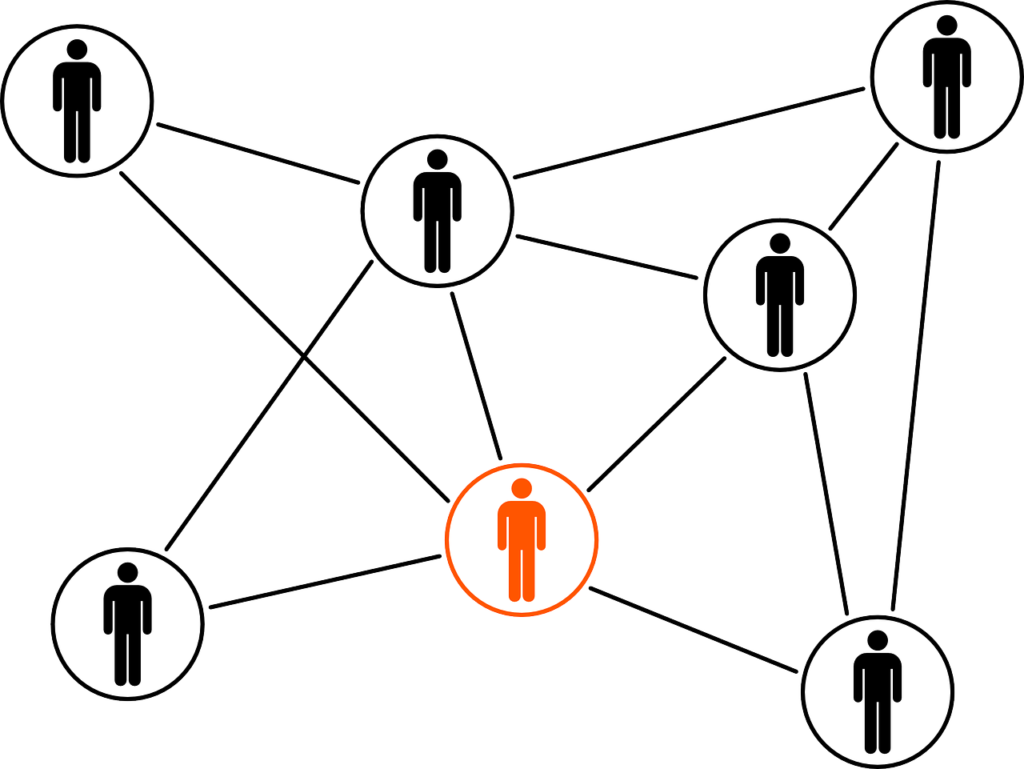
医療経営士試験の勉強は順調ですか?
さて、本ページでは医療機関の連携と在宅支援関連についてまとめていきます。
早速、始めていきましょう。
医療機関の連携
そもそも医療機関の連携とはなんでしょうか。
医療には急性期の治療期と回復期、そして療養期などがあることはすでに他のページで解説した通りです。
また病院や病棟についても、それぞれの特徴に合わせて区別されているのでした。
しかし患者さんの状態が急性期から回復期や療養期になったとしても、自動的に当該病院や病棟に移動できるわけではありません。
各病院や病棟間で患者さんの移動について相談を行って、医療機関同士で合意がなされなければなりません。
つまり単一の医療機関で全てが済むわけではないため、医療機関同士で協力が必要なのです。
そこで医療機関同士の連携が必要になってくるわけです。
では医療機関の連携についてみていきましょう。
病病連携とは
病病連携とは病院と病院間での連携です。
急性期治療病院と回復期リハビリテーション病院(以下リハ病院)間や、急性期治療病院と療養病院間による連携が病病連携に当ります。
例えば脳梗塞を発症して救急搬送となった患者さんを考えてみましょう。
まず救急搬送を受ける病院はいわゆる二次救急の病院となり、そこで脳梗塞の急性期治療を受けることになります。
脳梗塞とは脳内の血管が閉塞することで脳の機能が低下、もしくは機能しなくなる疾患です。
症状は脳のどの領域の血管が閉塞するかで変わります。
例えば左手を動かす領域の血管が閉塞すると左手が動かなくなり、口の周りの筋肉や舌を動かす領域の血管が閉塞すると呂律が回らなくなるのですね。
さて、脳梗塞の急性期では、血管の閉塞を解除し脳の機能が回復するように治療が行われます。
一般的には「血液をサラサラにする薬」の使用などが行われるわけです。
しかし、発症から時間が経過すればするほど脳機能の回復は悪くなり、麻痺などの身体症状も残りやすくなります。
そのため脳梗塞の治療は、脳の血管に対する直接的な治療の他にも、身体能力が落ちないように早期からリハビリテーション(以下リハビリ)を行うことが望ましいとされています。
発症早期であれば、急性期病院で脳血管に対する治療とリハビリが行われることになりますが、治療終了後も麻痺などが残存し、まだリハビリが必要な患者さんはどうなるでしょうか。
患者さんに必要なリハビリ期間は数日ではなく、ある程度長期的な日数が必要になると考えられますね。
急性期病院としては新たなに治療が必要な患者さんを受けるためにも、平均在院日数などを考慮した場合などにも、治療が終了した患者さんをリハビリで長期的に入院で診ていると、急性期治療の効率が悪くなります。
そのため、治療が終了したもののリハビリが必要だという患者さんは、リハ病院に転院していただくことが最良となります。
では、実際に転院とはどのような形で進むのでしょうか。
誰が音頭をとって、どのようにして決まるのでしょうか。
そこで転院の流れについて簡単にまとめてみます。
まず急性期病院で治療を受けた患者は、主治医の判断や、主治医・看護師・リハビリスタッフなどのチームカンファレンスなどにより転院が必要かなどが検討されます。
脳梗塞で入院し急性期治療が落ち着いた患者さんのカンファレンスの一例をみてみます。
主治医「脳梗塞の治療は順調に終了しました。あとはこの内服薬を継続します。患者さんの普段の様子はどうでしょう?」
看護師「元気にはなっていて食欲もあり内服管理も大丈夫そうです。右手足の麻痺も改善してきました。ただ退院後は一人暮らしで、自分で何でもできるか不安もありそうです。血圧にばらつきもあり家庭内血圧の測定をきちんと指導する必要があります。」
リハビリスタッフ「リハビリで患者さんの右手足の動きなどは概ね改善していますが、右手は利き手なので箸やペンの扱いにまだ時間がかかりそうです。また右足もまだ持ち上げる力が弱く、患者さんのご自宅にある階段昇降などを考えると、もう少しリハビリを行うのがよさそうです。」
主治医「それでは現時点では自宅退院ではなく、もう少しリハビリを進めてもらうためにリハ病院に転院をお願いするのがよさそうですね。」
あくまで例ですが、こんな感じで転院が望ましいのか検討されていきます。
では転院が望ましいと決まった後はどのような流れになるでしょうか。
まずは患者さんや、そのご家族などのキーパーソンに転院が望ましいことの説明が行われます。
そして転院することに納得していただいたら、転院先を検討することになります。
転院先は患者さんの状態を考慮して、主治医や医療ソーシャルワーカー(MSW:Medical Social Worker)などが適切考えられる病院の候補を決定します。
候補が決まったら、主治医が作成した診療情報提供書等をもとに候補病院に転院の依頼を行います。
依頼を受けた病院は、地域連携室などの転院受け入れ調節を行う部署があれば部署担当者、なければ病棟のベッドコントロールを行っている看護師長などが自院の病床の状況をみて転院可能な日時などを調節し、紹介元と合意することで転院が決定します。
さて、このような転院のやりとりが、たまにしか発生しないのであれば、都度転院先を検討してお願いする形でも問題ないかもしれませんが、脳梗塞の急性期患者が毎日搬送されてくるような病院ではどうでしょうか。
転院を検討する患者が毎日のようにいるのであれば、転院先候補をあらかじめ設定しておいて、転院先の病院と仲良くなっていた方が患者さんの受け渡しもスムースになりますね。
また、療養病院に入院中の患者さんが肺炎などを起こして積極的医療が必要になった場合などは急性期病院に転院していただくこともあります。
急性期病院は療養病院から急性期の患者さんを積極的に受け入れる一方で、急性期治療が終了した患者さんの療養病院の受け皿を確保しやすくなり、双方にとって良い関係となります。
このように連携することで患者さんだけでなく、医療機関にもメリットができます。
病病連携の最後に地域連携クリティカルパスについて記載しておきます。
地域連携クリティカルパスとは「急性期病院から回復期病院を経て早期に自宅に帰れるような診療計画を作成し、治療を受ける全ての医療機関で共有して用いるもの」になります。
ざっくりいうと、急性期病院から回復期リハ病院などの転院受け入れ病院間で、患者の治療や経過の把握を簡単にする連絡票みたいなものです。
例えば急性期病院のA病院と回復期リハ病院のB病院での地域連携クリティカルパスを考えます。
A病院では一般的な脳梗塞患者に対する治療内容と早期リハビリテーション内容はガイドラインなどに則り標準的方法が確立されているとします。
そして、ある一定の状態になったらB病院に転院をお願いしているとしましょう。
B病院は何人も転院を受けていると、同じような状態の患者さんを多く診療することになります。
それならば、A病院とB病院の間で「○○な治療を行って△△な状態になったらA病院からB病院に転院する。B病院では□□のリハビリを行って退院にもっていく。」という診療情報計画を事前に共有しておけば患者さんの治療・リハビリをスムースに進めることができます。
病診連携とは
では次に病診連携を考えます。
病診連携とは病院と診療所間での連携を指します。
診療所は無床診療所が多いわけですが、無床診療所ということは自施設に入院適応の患者さんが来院した場合には入院可能な病院に紹介する必要があります。
(治療可能な有床診療所に紹介してもいいのですが、病診連携という定義の中では病院に紹介といたします)
その際に事前に連携しておいて、入院患者を紹介しやすい病院があるとスムースにいきやすいですね。
お互い知らない者同士より知っている者同士の方が話がさくさくとまとまりやすいわけです。
無床診療所のホームページ等には、入院の状態であっても治療がスムースに進むように連携する病院があることを表記していたりしますね。
患者側も何かあったら、あの病院に紹介してくれるということが安心につながります。
診療所側は患者さんをすぐに引き受けてくれるととても助かりますし、病院側は入院患者さんを紹介してくれる診療所は貴重な存在になります。
また地域医療支援病院や特定機能病院の場合は、患者さんの逆紹介率を維持するためにも、安定した患者さんの外来診療を引き受けてくれる診療所の存在は欠かせません。
病診連携はとても重要な連携といえます。
病診連携の一つの形として開放型病床(オープン・ベッド)について説明しておきます。
開放型病床とは「病院のベッドの一部を地域の診療所の医師に開放し、双方の医師が共同で診療を行う」システムになります。
通常であれば診療所から紹介で入院になった患者に対して、診療所の医師が入院加療を行うことはありません。
しかし、診療所の医師が開放型病床をもつ病院にあらかじめ登録しておけば、入院が必要となった自分の患者を開放型病床に入院させることが可能になります。
患者にとってみれば、慣れたかかりつけ医が病院でも診療してくれるため安心に繋がります。
診療所の医師は入院中の経過などを詳細に把握することができるようになりますし、無床診療所でも入院設備のある病院と同様の医療が可能になります。
一方で、診療所の医師としては仕事量が増えることもありますし、病院の医師としては係わる医師が増えることで手間が増えたりすることがあります。
また開放型病床を利用すると、病院側・診療所側に診療報酬がつくのですが、これは患者の費用負担が増加することにもなります。
メリットだけでなくデメリットもあるため開放型病床を利用している診療所は少ないのが現状です。
診診連携とは
では続いて診診連携です。
これは診療所と診療所の連携ということになります。
昨今は複数の疾患をもっている患者が多く、かかりつけ医も診療科毎にいるというケースがたくさんあります。
例えば血圧は内科のA先生、腰痛は整形外科のB先生、メニエール病は耳鼻科のC先生などといった感じです。
また、内科は循環器科、消化器科、呼吸器科などに分かれているため、不整脈は循環器専門のD先生、逆流性食道炎は消化器専門のE先生、気管支喘息は呼吸器専門のF先生など、内科だけでもかかりつけ医が細分化されていく傾向にあります。
そこで診療所間での連携が必要になっていきます。
例えば、消化器専門医が内科として無床診療所で診療を行っていた場合に、入院が必要というわけではないけど心電図で気になる所見があったとしたら、循環器専門医が診療をしている診療所に紹介するわけです。
診診連携は患者にとって必要な医療を適切に提供するためにも、診療所の患者を確保するために重要です。
医科歯科連携
医療には医科と歯科があり、医師には歯科以外の診療を行っている医師(一般的な医師)と歯科医師がいます。
医科歯科連携とは、いわゆる一般的な医師と歯科医師との連携ということになります。
実は口腔内は人体のなかで最も汚いとされるほど、細菌などが多数存在しています。
概算ですが、よく歯を磨く人の口腔内細菌数は1000~2000億個、あまり磨かない人の口腔内細菌数は4000~6000億個、ほとんど磨かない人の口腔内細菌数は1兆個であると推測されています。
特に睡眠中は細菌が増加するため起床時の唾液1ml中の細菌量は、糞便1gの10倍量に相当するともいわれています。
つまり汚い話ですが、起床時の口腔内には糞便が10gあるということになります。
さて、何故このような汚い話を持ち出したかというと、口腔内の衛生環境が悪い方は誤嚥性肺炎になりやすかったり、心疾患や糖尿病などのリスクにもなることが明らかになってきています。
実は入院中の患者も口腔内環境がよくない方が少なくありません。
自力できちんと歯を磨くことができなかったり、そもそも歯周病がひどいといった状況の方もよくいます。
医師は口腔内環境の改善や歯周病の治療に関しては専門外ですから、歯科医師に対応していただく必要があります。
歯科を設置している病院は約2割にとどまっており、近隣の歯科医を含めた医科歯科連携が大切になってきます。
医療介護連携
医療介護連携とはざっくりいうと医療機関と介護サービス提供機関同士の連携です。
治療が終了し退院した後にも、訪問介護や訪問リハビリテーションなどの介護サービスが必要となることは珍しくありません。
ケアマネジャーが中心となって適切な介護サービスが検討されますが、その際には医療機関からの情報が欠かせません。
また介護サービスを受けている方が医療が必要となった際には、介護サービス提供者からの情報が医療機関にとっては役立ちます。
さらに患者によっては医療と介護が混在することもあり、医療介護連携はとても重要です。
現場で医療介護連携を実感するのは「急性期治療や回復期リハビリが終了後の退院時に介護サービスが必要となる時」や「介護サービスを利用している在宅の患者が、かかりつけ医に定期受診している際の情報のやりとり時」などでしょうか。
医療者側は患者の病名や病態、介護サービス時の注意事項などを介護者側に伝える必要がありますし、介護者側は患者の普段の状態、困っていることなどを医療者側に伝えることで、患者への医療・介護が適切になされていくことになります。
例えば、高血圧・心不全といった疾患をもっている患者であれば、医療者側は運動等の制限はあるかどうか、入浴時の血圧に上限はあるかなどを介護者側に提供します。
一方で介護者側は、普段の血圧や脈拍の報告や食事摂取の状態などの他に、昼の内服薬は飲み忘れが多くなっているとか、実は便秘で困っているなどの状態を医療者側に提供します。
このように医療介護連携がスムースにいくことで、患者に対する効率的・適切な医療介護が可能となっていきます。
在宅療養支援診療所・病院
在宅療養支援診療所と在宅療養支援病院は、24時間365日の連絡体制や訪問看護との連携を行っている医療機関です。
在宅療養支援診療所はその名の通り診療所で、在宅療養支援病院は200床未満の病院(医療資源が少ない地域など別に定められた地域では240床未満)、又は半径4km以内に診療所が存在しない病院になります。
また病院では往診担当医は、当直医とは別の医師でなければいけません。
機能としてざっくり説明すると、いわゆる在宅医療を充実させた医療機関といえます。
そもそも在宅医療とは、「がん」などの疾患や高齢による体力低下など、様々な理由から医療機関に通院が困難な患者が在宅で医療を受けることができるようするシステムです。
在宅医療を行うシステムとして、訪問診療や往診、訪問看護、訪問リハビリテーションなどがあります。
訪問診療と往診の違いですが、訪問診療とは「週1回木曜日」など定期的になされるものであり、往診は患者の体調が突然悪化したときに患者や患者の家族からの依頼を受けて行うものになります。
以前と比較して在宅医療でできることは増えてきており、酸素療法や人工呼吸療法、中心静脈栄養療法や人工透析なども可能になってきています。
国の方針として昨今は看取りも在宅でという流れもあり、在宅診療が推し進められてきました。
その一環として在宅療養支援診療所・病院が創設されたのですね。
在宅療養支援診療所・病院になると医療機関側のメリットとして「在宅時医学総合管理料」や「在宅がん医療総合診療料」の算定が可能になります。
では在宅療養支援診療所・病院の要件をみてみます。
- 24時間連絡を受ける体制の確保
- 24時間の往診体制
- 24時間の訪問看護体制
- 緊急時の入院体制
- 連携する医療機関等への情報提供
- 年に1回、看取り数等を報告している
在宅支援診療所・病院は徐々に増加してきており、2020年7月の届出数は在宅支援診療所が14,615、在宅支援病院で1,546となっています。
在宅診療を推し進める診療報酬改定としては2016年の改定で在宅医療専門の医療機関が認められました。
それ以前は在宅診療だけの診療所などは認められていなかったのですね。
しかしながら在宅診療には移動などを含めて一人当たりの診療に時間がかかることから、午前は診療所で通常外来で午後は訪問診療を行うなどでは手が回らなくなってきました。
そのため一定の条件を基に在宅医療専門の医療機関が認められたのです。
- 外来診療が必要な患者が訪れた場合に対応できるよう、診療地域内に2か所以上の協力医療機関を確保していること(地域医師会から協力の同意を得られている場合はこの限りではない。)
- 在宅医療導入に係る相談に随時応じ、患者・家族等からの相談に応じる設備・人員等が整っていること。
- 往診や訪問診療を求められた場合、医学的に正当な理由等なく断ることがないこと。
- 緊急時を含め、随時連絡に応じる体制を整えていること。
そして在宅専門医療機関の診療報酬上の評価は下記の一定の条件を満たすと在宅支援診療所と同様になります。
- 在宅患者の占める割合が95%以上
- 5か所/年以上の医療機関からの新規患者紹介実績
- 看取り実績が20件/年以上又は15歳未満の超・準超重症児の患者が10人以上
- 施設系を利用している患者割合が70%以下
- 要介護3以上や重症患者の割合が50%以上
そして2018年の診療報酬改定で、一般診療所が24時間の往診と連絡体制を構築した場合の評価が新設されました。
これは、日中業務しか行っていない一般診療所にも、かかりつけ患者に対しては24時間体制で在宅までカバーしてほしいという国の方針の表れといえますね。
◇
◇
◇
本ページは以上です。
また次の記事でお会いしましょう!